タイトルとは逆に、「風雲児たち」から触れさせていただく。
「風雲児たち」とは漫画です。詳しくはwikiをご参照いただきたいが、
まあそれはもう大作です。絵画でいえば「ナポレオンの戴冠」くらいな感じ。
そりゃ、長いマンガはいくらでもある。「ワンピース」は60巻超、「ドラゴンボール」40巻超、
「美味しんぼ」104巻超、……え?「こち亀」って……174巻も出てたのか!?
長いとは聞いていたが、150巻は超えてないと思っていたよ。
いやまあ、それはさておき。
そういうのと比べれば「風雲児たち」20巻、「風雲児たち 幕末編」現行18巻というのは、
数としてはそこまで特筆すべきものではない。
が、こいつはね。それらと比べても大作だよ。えらい仕事だよ。頭が下がるよ。
マンガに対して頭が下がるというのも、わたしにしてはなかなかない状況だ。
もしかしたら唯一かもしれない。
絵柄がギャグで好みではなく(そして中身も若干ギャグなので)、最初は全然興味なかった。
薦められてしぶしぶ読んだ口なのだが、いやー、これは読みごたえがありますよ。
どんだけ調べてるかねー。下手な物書き……というより、上手な物書きに負けない下調べ。
むしろ文字だけの物書きよりハードルは高いかもしれない。
マンガが絵で見せることを宿命とする以上、必要とする資料は多分文字書きよりも多いだろう。
一次資料というのは、根本的に文字によるものが圧倒的な筈で、図を探すには苦労も多いと思う。
しかし歴史と正面から四つに組んだ漫画であるため、作者は能う限りきっちり描こうとするわけで。
(といっても基本はギャグ漫画なんですけどね)
――頭が下がります。
実は「風雲児たち」は、最初は幕末をメインに描くよう依頼された漫画だったらしいのだが……
(この辺はwikiに詳しいけれども)
幕末を描くには江戸時代の始まりから描かないと意味がない、という信念に基づき、
作者は関ヶ原から話を始めてしまった。幕末にようやく辿りついたところまでが「風雲児たち」。
そしてタイトル的には「風雲児たち」に対して「風雲児たち 幕末編」とまるで番外編のように
なってしまったが、むしろ本題は幕末編の方にあるわけですな。
つまり現行18巻だが、今後おそらくもっともっと続く……。
大作にありがちだが、未完はダメだぞ。ちゃんと完結してくださいよー。みなもと太郎。
この漫画を読んだおかげで知ることが出来た人はいっぱいいたし、
名前しか知らなかった人も血肉を持った存在として捉えることが出来たし、
なんというか、大変お得な漫画。お得っていうか……まあこういうことを書くと
月並みでもあり、褒め言葉としてはむしろマイナスかもしれないが、
大変勉強になります。網羅的だし。
※※※※※※※※※※※※
さて「文政十一年のスパイ合戦」。面白かったが、
この本は「風雲児たち」を読んでいたからこそ面白かったという側面があるんだなー。
「風雲児たち」でわりといい人に描かれていた高橋作左衛門が、この本ではけっこう嫌な奴とか。
素朴を絵に描いたような最上徳内がヨーロッパ学術界に野心を持っていたとか。
狷介な間宮林蔵が……彼はそれほどギャップはないんだけど、この本での方が、
わりとシンプルな性格として捉えられていたかな?
本自体の価値としては、真面目に資料に当たっていること。
かなりいい仕事だと思うよ。信頼感がある。
真面目すぎて、正直、検証部分の細かいところはちょっと面倒で飛ばしたが。
もう少し書き方に工夫があればもっと面白いものになっただろうね。
やり過ぎは良くないけど、こういう本ならもう少し芝居っ気があっても良かった。
しかし結論部分は若干疑問がある。
シーボルトを餌に島津重豪、ひいては薩摩藩を牽制するというのが幕府の目的だったのだ、
というのをシーボルト事件の真相として結論しているんだけど、
それにしては流出した資料が大掛かりすぎないか……。
鯛で海老を釣るとまでは言わないが、伊勢海老で鯛を釣るような真似をしているように思える。
(伊勢海老が鯛のエサになり得るかどうかは知りません)
まあ当時の日本は国際情勢に全く疎い、“世界の赤子”状態だったんだろうから、
情報の優先順位の付け方もおそらく妥当性を欠いたのだろう。
幕末の、躍動する時代感はすごい。シーボルト事件でさえ幕末における一挿話でしかないんだもの。
まあわたしは、あんまり複合的に躍動する時代には生きたくない気がするけどね……。
一般庶民にとっては、平穏無事な江戸中期後期あたりが多分生きやすいですよ。
双葉社
売り上げランキング: 310350

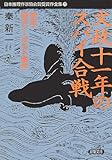

コメント