これはたしか、立花隆の書評本で読んでリストアップしたんだったかな。
すごく面白かった。
海野弘は数十年前、アール・ヌーボー、アール・デコの著作で出会ったんだった。
わたしはてっきりその分野の研究者だと思っていたのだが、違ったんですね。
「太陽」の編集者だったらしい。なるほど。
今回、著作物のジャンルの広さに驚いた。同名の別人かなと思った。
さらに冊数に驚いた。こんなに書いてるのか。
そして、この本を読んでその面白さにさらにびっくり。
小説。ですよね。これは。
多分海野弘が、その多読のうちに見かけた、江戸期のちょっと変わった小話を骨子に、
その周りに自由に肉づけをして作った短編だと思うんだ。
たとえば最初の話は、題名が「結び人」。
江戸期の有職故実の研究家である伊勢貞丈が、吉原で評判の結びの名人を訪ねる。
名人の名は新吉といい、遊女の帯をしめればその形はいつまでも崩れず、飾り結びは宴会芸にもなり、
あげくは酔っ払いを絡め取る捕縄術さえ操る。
伊勢貞丈は常々、結びの技術を後世のために書き留めておきたいと思っていた。
新吉に話を聞き、その他の伝聞や自分の知識も加え「包結図説」という書物にまとめた。
――と、おそらくこれは実際にあったことなんだろう。
だがその新吉が京都から江戸に流れてきたとか、それは惚れた遊女が首をくくったからだとか、
その遊女は緊縛好きで、首をくくった縄は、新吉が教えた結び方で結ばれていたとか――
そういうのは創作だろう。
本を(とりわけ雑学系の本を)たくさん読んでいる人は、面白い小ネタにちょくちょく出会う。
しかし小ネタはあくまでも小ネタであり、それで何かひとまとまりの文章を書くというのはなかなか難しい。
でも出来れば、面白いネタは出来る限り世に広めたいですよね。
この本は、そういう小ネタを活用して、上手に1冊にまとめた本。
お手柄だと思ったし、面白かったし、なかなか。
……惜しむらくは、途中に入る百科事典的解説が、今一つ極まってなかったこと。
そのかわりに関連図書の紹介を入れたら、これはもうスバラシイ一冊になっていたと思いますよ。
いや、最初「包結図説」の解説だったから、頭から関連図書の紹介だと思って、そのウマさに
目を瞠ったわけですよ。ネタで読ませ、創作部分で読ませ、さらに本まで紹介するとは!
こんなの見たことない!スゴイ!
でも実は本の紹介じゃなかったのでね。
本の紹介じゃなかったのはしょうがないとして、その解説もまったくユルい感じで、啓蒙される部分がない。
小説部分の後追いでしかない。小説で読んでからそれを補足するという機能は全くない。
むしろ最初にそれを持ってきたら、まだ意味があったろうにねえ……
まあでもその部分のマイナスを差し引いても面白い本でしたよ。
わたしが一番好きなのは「花火師」。
これもネタの部分としては「文政年間の記録に秩父の村で大掛かりな花火があったという通報があり、
役人が調べたが、花火師を見つけることができず、おそらく村人が狐に化かされたのであろう、
ということになったそうである」……末尾のここだけだと思うのよ。
海野弘はそこから物語を描く。
禁制のオランダ花火をどうしても上げてみたくて、とどのつまり鍵屋を破門されてしまった腕のいい花火師。
免許を取り上げられてしまったので、花火を上げたら罪人として捕まってしまう。
そこへ、悪仲間が一人の男を連れてくる。
聞けば男は、秩父の山奥から江戸へ来て、花火を上げてくれる花火師を探しているという。
贅沢禁止で、田舎では芝居も花火もやってはいけない。江戸でさえ花火は大川でしか許されていない。
それなのにその男は花火を上げてくれと頼むのだ。
私の村も山奥にあります。ほとんどの村人は、山からどこにも出ないで、一生を過ごします。
旅まわりの薬屋がくると、みんな集まって江戸の話を聞きます。いつか花火のことを聞いて、
年寄りから子どもまでが夢中になりました。「花火が見たいなあ」とみんないいました。
そのうちに、江戸の花火師を呼ぼうという夢のような話がふくらんできたのです。
男は村の名主に呼ばれ、五十両を渡される。
みんなで集めた金、五十両。これを持って江戸に行き、花火師を連れて来てくれ。
村のみんなに花火を見せてやりたい。
だが、御禁制を破ることなので、連れてくるのは無理かもしれない。
その時はお前がわたしたちの代わりに花火をしっかり見て来てくれ。
わたしたちはお前の話を楽しみに待っている。
花火師は打ち上げを承知した。
ひそかに材料を集め、秩父へ送った。送る手配は男を連れてきた悪仲間がやった。
悪仲間も、故郷は上州の山の中。同じような山の村に住む人に花火を見せてやりたかったのだ。
やがて花火師も秩父の村へ行った。“花火が上がる”ひそかな噂を聞きつけて、遠くからも人が集まった。
花火師は立派なオランダ花火を打ち上げて見せた。
村人は美しい花火を夢中になって見物した。「夢屋!」という大きな掛け声が上がった。
……もう、これが泣けてねえ。
五十両というのは海野弘の筆先一つの話だろう。しかしそんな大金を、一瞬の美しいもののために
遣おうというその気持ちが……泣ける。
駄目だったらお前が代わりに見て来て、そして話をしてくれ、というのも泣ける。
そこには、やむにやまれぬ情熱がある。未知なる美しいものへの憧れ。
もちろん、これは絵空事です。有り得たかもしれない話ではない。むしろ有り得ない話だ。
禁制の花火を、命がけで上げると――村人全員が合意するはずもない。
一人でも納得できない人がいれば成り立たない話だ。
命がけで見ず知らずの村のために上げようという花火師が――これは、いる筈がないとは言わないけれども、
まあいるかどうかは怪しい。
そして上げて欲しい、上げたい、と双方揃ったとしても、
実際に材料を運んだり打ち上げ準備をしたりするのは、現実的に困難と言わざるを得ない。
でもね。いいよね、こんな話は。
有り得た話ではなく、あって欲しかった話として、こういう話は好きだ。
ちなみに他の話はもっとあり得る話なので、本当にこういうことだったのかもしれないな、と思う。
「花火師」は――海野さんのロマンティックが止まらなかった一篇ということで。
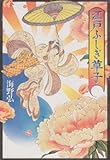

コメント