ドヴォルザークのオペラ。
タイトル初耳。というか、ドヴォルザークって「新世界より」しか知らん。
言葉がわからない上に、ストーリーの知識も皆無ではどうしようもないので、
事前にあらすじはチェックしていた。どんな話かというと、つまりは人魚姫。
これもそうだし、フーケーの「水妖記」もそうだけど、この話の大元はどこから来てるんだろうね。
水魔は人間からすれば異界の生物で、畏怖の存在であったはずだ。人知の及ばぬもの。
水に棲み、人を誘惑し水底へ引きずりこむ。いわば敵対関係であるべき水魔。
その側に立った「人魚姫」を初めとする物語は、自然発生というよりは、より創作の匂いがする。
どこでこの話が生まれたか知りたいものだ。
それはさておき。
第一幕。
冒頭、舞台は蒼い薄闇。
シルエットで大きい人物と小さい人物が現れ、ごくゆっくり歩を進めていく。
どのくらいのゆっくりさかというと、能の移動速度を思い出したくらい。
すれ違いざま、大きい人物は怒りを露わにし、片手を小さい人物に向けて相手を呪う仕草をする。
小さい人物はそれを受けて、後悔なのか苦悩なのか、頭をかきむしる。
彼らがどういう人物なのかは、シルエットでもあり、衣裳もマント様なので、
この時点では観客はわからない。
照明が入ると、水の精たちが楽しげに歌っている。
歌い手は第1から第3の水の精の3人。背後ではやはり水の精として10人程度のバレエ。
そこへ水の世界の王(ごとき存在)として威厳ある男性が現れる。
水の精たちは彼が結婚相手を探しているといい、「私たちの中から早く選びなさいよ」などと
からかって戯れる。
しかし彼の娘で、水の精の1人であるルサルカ――これは水の妖精の一般名詞であるので、
これが主人公の名前なのは妙な気がするのだが(でも「人魚姫」も人魚姫だしね)――が登場し、
人間の王子に恋をしてしまった、人間になりたいと切々と訴え始めると、
水界王は途端に苦悩に見舞われる。彼は言葉を尽くしてルサルカを翻意させようとするが、
彼女は拒絶する。水界王は最終的に、魔女イェジババへ相談するようルサルカに言わざるを得ない。
白いドレスに黄金の髪が美しいルサルカが、黒衣のイェジババへ会いに行く。
ルサルカがその願いを話すと、彼女は願いをかなえるという。
しかし愛する人の裏切りに遭えばその時は命はないと。
ルサルカはその条件を受け入れ、人間に姿を変えてもらう。
水のほとりに立つ、人間になったルサルカ。
そこへ狩人たちが近付いてくる。その中にはルサルカが恋する人間の王子もいた。
王子は神秘的なルサルカを一目見て恋に落ち、おそらく彼の唯一の(唯二くらいか)
見せ場であるアリアを歌って、城へ連れて帰る。
第2幕。
第1幕は水の精たちが棲んでいる森の中だったが、雰囲気ががらりと変わってお城の中。
宴会の準備が進められている。
登場するのは狩場管理人と料理人見習の少年。宴会の準備をしながらの彼らのやりとりで、
この日が王子とルサルカの結婚式だということがわかる。
しかし狩場管理人はルサルカに不審をもっており、
王子の結婚相手としてあの娘(=ルサルカ)が相応しいかどうか心配する。
ルサルカは見知らぬ人間の世界で孤立している。
口がきけない彼女は誰とも繋がりを作れず、頼みの綱の王子さえ彼女にもう興味をなくしている。
そこへ現れる異国のプリンセス。黒いドレスをまとった。
王子はプリンセスに惹かれる。彼らは踊り始める。
ルサルカはそれをただ見ていることしか出来ない。優雅に繰り広げられる群舞。
そんなルサルカを案じて、水界王が彼女に会いに来る。
もう王子への愛は望みがないことを断言し、ルサルカを連れ戻そうとする。彼女は取り乱す。
そしてその頃、黒いドレスのプリンセスは王子を誘惑し、王子は虜になり始めていた。
ルサルカはその場面を見てしまい、思わず王子に駆け寄ってすがるが拒絶される。
水界王はうちのめされたルサルカを連れて帰る。
第3幕。
水の世界に帰ったルサルカ。しかし彼女にはもう望みはなく、抜け殻のようになっている。
彼女は選ばなければならない。王子を殺して元のように暮らすか。あるいはこのまま死んでいくか。
だが彼女に王子は殺せない。
王子がルサルカに赦しを請うためにやってくる。2人は静かに死んでいく。
以上、ネット上のサイトと買ってきたCDの解説書をチラ見しつつ、
記憶(感知出来たもののみ)に基づいて書いたあらすじ。正確性は70%くらいだろうか。
※※※※※※※※※※※※
見ただけで如実にわかるように、後に行くに従って情報量が少なくなる。
……いや、駄目だったのだ。眠くて。最終的には早く終わらないかな、と願ってしまった。
もうちょっと眠くない時に行ければ良かったんだけど。
それに……歌い手のせいにするのもずるいかもしれないが、王子に迫力がなかった。
王子に迫力がなければ結末が締まらない。
ちなみに主要キャスティングは以下の通り。
ルサルカ Maria Haan
王子 Peter Berger
水界王 Stefan Kocan
イェジババ Dagmar Peckova
異国のプリンセス 同上
(なお、第1の水の精として、Yukiko Srejmova Kinjoの名前あり)
一番印象に残ったのは水界王。体躯は堂々として、声は朗々として、
うんうん、これこれ。聴きに行って良かったと思えた。
ルサルカも美しい声だった。買ってきたCDよりも、舞台で見た方の声が甘くて叙情的。
多分本人の年齢もより若い。それゆえ雰囲気が出せたような気がする。
この2人は満足な感じ。
イェジババは、うーん、いまいち好きじゃなかったな。歌い方とか声質が。
何しろ魔法使いの役柄だから、気持ちいい旋律は歌わないだろうし、
そういう意味でも好きになれないのはしょうがないのかもしれないけど。
王子となると、上で言ったように、何だか迫力がないことおびただしい。
ルサルカと王子の力量が均衡してこそ最後が盛り上がるというものだろうが、
だいぶ差があったように感じられた。
ただ、難しいキャスティングではあるのかな。王子はそれほどいい役柄じゃないので、
いい歌い手を持ってくるのも難しかろう。
ところで、今回イェジババと異国のプリンセスを1人の歌い手がやっていた。
これは本来、イェジババがアルト、異国のプリンセスがメゾソプラノらしいので、
普通はそれぞれ1人ずつキャスティングをするはず。買ってきたCDでも別な歌い手。
今回、2役をさせたのは新機軸なのだろうと思う。
作品自体を理解しているとは到底言えないわたしが言うのもなんだが、
これはわりと成功しているのではないか。少なくとも一つの解釈ではあるよね。
複数のサイトであらすじを読んで思ったんだけど、この異国のプリンセスというのが、
どうも謎めいた存在で。というより、謎めいた存在なんだか、それとも単にエキゾチックな美女
というだけの存在なのか、はっきりしない。
オペラなんて、ストーリー的には無理がありまくるもので、この「ルサルカ」も、
そういう意味では脇が甘々なんだけど、その一端を解消しようという努力をしたのかな。
実は、冒頭すれ違う2人の人物は、大きい方が水界王、小さい方がイェジババでした。
人物のシルエットから判断するに。
そうすると……こういうことになるのかな?
イェジババは、ルサルカの願いをかなえてやっておきながら、王子を誘惑することによって
ルサルカを結果的に死なせることとなった。それを父である水界王は責め、
イェジババは良心の呵責に苦しむ。
……それはそれで無理のある流れのような気もするけど。でもまあオペラですから……。
オペラは総合芸術、とよく言われる。
普通オペラを考える場合、歌い手・舞台美術・オーケストラの3つを思い浮かべるが、
一般人にはあまり思い及ばない要素として、実はもう一つ大きなものがある。それは舞踊。
舞踊はアレンジの部分なので、長短伸縮自在。かなり融通がきき、独自性を出すことが出来る。
今回の舞台は現代舞踊としてのバレエの要素が強かったのではないか。
水の精とか。宴会の群舞とか。まあ王子のお供の狩人なんかも。
歌い手だけが舞台上にいるという時間はそれほど長くなかった。全体の半分以上は
舞踊が登場していたと思う。目を楽しませる要素も大事ですからね。
歌い手は、歌っている間は複雑な動きは出来ないし「なんとか動きを」と思って
演出家も苦心するんだろうが、身振り手振りもネタがつきてしまうしね。
だがしかし、あの男性ダンサーは一体なんなのか。
頭を剃り上げて。衣裳は(まるで小学校の体操着のような)白い短パン一丁の。
この男性ダンサーが相当に出てくる。群舞でも1人別な動きをして目を引いているし、
単独でもけっこう出てくる。
彼は何の意味を帯びているのだろう?意味なく出てるわけではないよね?
何の象徴なのかとか、全然思いつかなかった。「ダレ?」状態。
まあ鍛え上げられた肉体は見事で、ダンサーとしても上手そうだったからいいのだが。
舞台美術的には吊り物が素敵だった。それは例えば宴会のシャンデリアを象ったものだったり、
睡蓮をイメージしたものだったり。けっこう大きくて、物体としては縦横1メートル程度。
特に睡蓮は、舞台上でダンサーが踊っている時に、人数分が上からゆっくり下がってきて、
最終的には1人1つを手にして(←取り外せる)ダンスに取り込む、などをするので印象が強かった。
舞台上に池を作っていたところも少々驚いた。実際に水が張ってあり、その中を歩いたり
水をはねさせたりする。ごく浅いもので、せいぜい水深は5~10センチくらいだろう。
わたしは2階のセンターバルコニーに座っていたので、上からその池がよく見えたが、
平土間に座っていた人たちは多分見えないんだろうね。
水の精の一人がハープの音色に合わせて(つまり音楽的にはハープで水を表している)、
手で水を優雅にかき回し、水音をたてていたりした。これは微妙だと思っていた。
楽器で水を表現する部分があるんなら、実際の水音は蛇足というものだよ。
水の動きはきれいだったけど。
その他の舞台装置は抽象系。
長方体のような物体を、段差にも使えば宴会のテーブルにもするというような。
転用して色々に見立てさせる。
高低差と奥行きにずいぶん気を使っていたようには見えた。
だが、見立ての舞台装置にありがちな、多少間が抜けているようなところはあった。
以上、思ったことをとりとめなく書き連ねてみたが。
……結局、もう少し知っているオペラの方が楽しめただろうな。
まあシンプルな話なので、楽な方だったんだろうけど。
だが、字幕を読むのにも忙しく、その他に歌を聴き、ダンスを見、舞台装置をチェックし……
というような見方になってしまうので、要素が溶け合った1つの作品として楽しめたかというと、
そこまでではない。字幕が舞台のかなり上の方にあるので、字幕を読んでいると
舞台で進行していることを見逃すし。
それから、やっぱり眠くない時の方が良かった。
「フィガロの結婚」に行くことも出来たのだが。
でも、国民劇場でドヴォジャックの作品を聴くことは意味があったと思う。
箱のデザインから判断するに、わたしが買ってきたのはまさにこのCD。
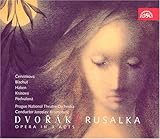

コメント